ファイル名と保存先の設定
[プロパティ]からデータのファイル名と保存先を設定することができます。設定した保存先フォルダとファイル名は、本アプリケーション終了時に履歴として保存されます。
ファイル名を変更する
注意
- ファイル名が重複しているとデータ吸い上げを実行できません。任意でファイル名を指定する場合はご注意ください。
- 任意でファイル名/保存先を変更する前に[保存ファイル名の履歴機能について]をお読みください。
参考
- プロパティ画面を開くには、データ情報一覧から保存するデータをひとつ選択し、右クリックして表示されたコンテキストメニューから[プロパティ]を選択します。
- 初期設定のファイル名は"機種_子機名_データ収集日時"です。(例: RTR-501_Unit01_2010-11-26-004659.trx)。
無線通信で吸い上げたRTR-574/576の記録データには、データ判別の文字列が自動的に付加します。 - 初期設定の保存先は"Documents\TandD Corp\RTR-500DC for Windows\data" です。
[ファイル名を規定の書式で指定する]か、[ファイル名を任意に指定する]にチェックをします。
[ファイル名を規定の書式で指定する]場合は、コンボボックス内の6つの書式から指定してください。
ファイル名を任意に指定する場合は、[ファイル名の指定]ボタンをクリックし、保存先のファイル名を指定してください。
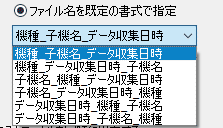
データ判別の文字列について
RTR-574/576 の記録データは、データコレクタで吸い上げたときの通信方法が無線通信だった場合、2つに分かれて保存されます。無線通信で吸い上げた記録データには、記録データの吸い上げを行う際にデータ判別の文字列をファイル名の末尾に付加します。
_IU : 照度と紫外線強度のデータに付加する文字列です。(例: RTR-574_Unit0574_2011-01-07-171339_IU.iur)
_TH : 温度と湿度のデータに付加する文字列です。(例: RTR-574_Unit0574_2011-01-07-171339_TH.iur)
_CO2 : CO2のデータに付加する文字列です。(例: RTR-576_Unit0576_2011-01-07-171339_CO2.thc)
この文字列は、[ファイル名を規定の書式で指定する]を選択したときに必ず付加されます。
[ファイル名を任意に指定する]を選択したときは、データ情報の取得*を行うまで付加されません。
*データ情報の取得が行われるタイミングは、[データ情報取得]をメニューから行うとき、[データ削除]をメニューから行うとき、本アプリケーションを再起動したときです。
保存ファイル名の履歴機能について
本アプリケーションでは吸い上げデータの保存先フォルダとファイル名を、アプリケーション終了時に履歴として保存します。
履歴のキーワードは機種と子機名です。データコレクタからデータ情報を取得する際に、この履歴を検索してキーワードが一致するデータに対して、自動的に[吸い上げデータフォルダ]と[吸い上げファイル名]を表示します。
データ情報の取得が行われるタイミングは、[データ情報取得]をメニューから行うとき、[データ削除]をメニューから行うとき、本アプリケーションを再起動したときです。
また、長期間(150日)データ一覧に表示されない機種−子機名の履歴は自動的に削除されます。
この機能は、ある条件においては意図しない[吸い上げデータフォルダ]と[吸い上げファイル名]を表示する場合があります。以下3つの具体例を参考にしてください。
例1: 同じ子機の吸い上げデータを別々のフォルダに保存したとき
機種RTR-501/子機名TEST01の記録データをデータコレクタで2回吸い上げた場合、データコレクタ内には"RTR501
TEST01"というデータが別々のデータ収集日時で2個存在しています。この2個のデータをデータAとデータBとします。
データAをC:\Data\AAAに、続いてデータBをC:\Data\BBBに保存するように[プロパティ]で設定したとします。本アプリケーションを終了しなければ、データ情報一覧に表示されている[吸い上げデータフォルダ]と[吸い上げファイル名]は設定通りに表示されています。しかし、データ情報の取得が行われると、保存ファイル名の履歴機能により、同じ機種と子機名の[吸い上げデータフォルダ]と[吸い上げファイル名]は最後に設定したデータを表示します。
例1の場合はデータBを最後に設定したので、データ情報の取得が行われると、データ情報一覧では"RTR-501 TEST01"の[吸い上げデータフォルダ]はすべてC:\Data\BBBになり、[吸い上げファイル名]もデータBの設定に従います。
例2: 同じ子機の吸い上げデータを任意のファイル名を設定して保存したとき
機種RTR-501/子機名TEST01の記録データをデータコレクタで2回吸い上げた場合、データコレクタ内には"RTR501 TEST01"というデータが別々のデータ収集日時で2個存在しています。この2個のデータをデータAとデータBとします。
データAをC:\Dataに"Sample1.xxx"というファイル名で、続いてデータBをC:\Dataに"Sample2.xxx"というファイル名で保存するように[プロパティ]で設定したとします。データ情報の取得を行わなければ、データ情報一覧に表示されている[吸い上げファイル名]は設定通りに表示されています。しかし、データ情報の取得が行われると、保存ファイル名の履歴機能により、同じ機種と子機名の[吸い上げファイル名]は最後に設定したデータを表示します。
例2の場合はデータBを最後に設定したので、データ情報の取得が行われたデータ情報一覧では"RTR-501 TEST01"の[吸い上げファイル名]はすべて"Sample2.xxx"になります。
例3: 同じ名前を持つ子機2台が別の無線グループにあり、任意のファイル名を設定して保存したとき
機種RTR-501/子機名TEST01が2台あって、別の無線グループ上に存在しているとします。データコレクタでそれぞれの記録データ吸い上げた場合、データコレクタ内には"RTR501 TEST01"というデータが別々のデータ収集日時で2個存在しています。この2個のデータをデータAとデータBとします。
データAをC:\Dataに"Sample1.xxx"というファイル名で、続いてデータBをC:\Dataに"Sample2.xxx"というファイル名で保存するように[プロパティ]で設定したとします。データ情報の取得を行わなければ、データ情報一覧に表示されている[吸い上げファイル名]は設定通りに表示されています。しかし、データ情報の取得が行われると、保存ファイル名の履歴機能により、無線グループが別で2台の子機であったとしても、同じ機種と子機名のために、[吸い上げファイル名]は最後に設定したデータを表示します。
例3の場合はデータBを最後に設定したので、データ情報の取得が行われたデータ情報一覧では"RTR-501 TEST01"の[吸い上げファイル名]はすべて"Sample2.xxx"になります。